ø¢27-1-NT-(A)@mÖWã¼Ìa¶n
@@@@@öEnipp.58-59jÉæêÎAQÂÌßðæè§ÚÉѯé]®\¢
ªÜ¾BµÄ¢È©Á½ndÅÍA¶Æ¶ÆðPÉ and Åñ¾Àñ\¢ÅlXÈ]
®\¢ÌÓ¡ð\µÄ¢½B...odÌæ¤ÈÖWß\¢ÉéÜÅÉÍA\¢IÉà¢
©ÌiKªKvÅ Á½B1) Í»ÌBðÈPÉ}®»µ½àÌÅ éBip.59)
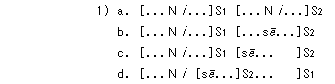 iS ͶAmi ͯêl^¨ðw¦·é¼ð¦·j
o_ÆÈéÌÍA¯¶àÌðw·¼ðÜñ¾QÂ̶ÌÊÚ±\¢1-a)
Å éBQÂÚÌ¶É é¯êw¦Ì¼ÍAJèÔµðð¯é½ßÉ1-b) Ìæ¤Éã
¼»³êA³çÉr2̶ªÖ®©³ê1-c)ÆÈÁ½B±êªÖWß\¢Ì´^Å éB
ÌiKÉÈéÆAr2S̪iå¶j̼iæsj̼ãÌÊuÉ®©³ê 1-d)
ÆÈéB±ÌöEnÌðàÌv_ÍÌQ_Å éB
@@(i) ÈOÍ]®\¢ªÈ©Á½Biand ÉæéÊ\¢ÌÝj
iS ͶAmi ͯêl^¨ðw¦·é¼ð¦·j
o_ÆÈéÌÍA¯¶àÌðw·¼ðÜñ¾QÂ̶ÌÊÚ±\¢1-a)
Å éBQÂÚÌ¶É é¯êw¦Ì¼ÍAJèÔµðð¯é½ßÉ1-b) Ìæ¤Éã
¼»³êA³çÉr2̶ªÖ®©³ê1-c)ÆÈÁ½B±êªÖWß\¢Ì´^Å éB
ÌiKÉÈéÆAr2S̪iå¶j̼iæsj̼ãÌÊuÉ®©³ê 1-d)
ÆÈéB±ÌöEnÌðàÌv_ÍÌQ_Å éB
@@(i) ÈOÍ]®\¢ªÈ©Á½Biand ÉæéÊ\¢ÌÝj
 (ii) QÔÚÌmÍAm»Ìą̀`m``¨¶ªÚ®i
(ii) QÔÚÌmÍAm»Ìą̀`m``¨¶ªÚ®i ¶jA
¶jA
 @@@ ÆÏ»µ½B
ø¢27-1-NT-(B)@mÖWã¼Ìthat ƼßÌ thatn
@@@@@Quirk et al. (1985, p.1047) ÍAsubordinate clauses ƵÄAnominal,
adverbial, relative, comparative ð °Ä¢éB±Ìrelative clause ͱÌ{Ì`ß
Å èAQuirk et al. ÍÀãAm/`/`cßðRÂÆà subordinationÆÊuïĢ
é±ÆÉÈéB
½¾µAQuirk et al.(1985, p.989ff)ÍAmßA`cßðÂé conjunction
ÌÝð subordinator ÆÄñÅ¢éBÖWã¼Ì that ÍAmßðÂé that ÆæÊ
µÄ subordinator ÅÍÈ subordination marker(p.1006) ÆÄÔB
The relative pronoun is to be distinguished from the subordinator
@@@ that, which does not operate as an element in the subordinate clause.
±Ì{ÅÍABurton-Roberts (pp.192ff)ÈÇƯlAmßA`cßA`ßð
(CVT{rÆ¢¤)ÐÆÂÌ`Å¡ÀÑÉÆç¦éBàÁÆàAmßð¶Ýo· that Íó
@@@ ÆÏ»µ½B
ø¢27-1-NT-(B)@mÖWã¼Ìthat ƼßÌ thatn
@@@@@Quirk et al. (1985, p.1047) ÍAsubordinate clauses ƵÄAnominal,
adverbial, relative, comparative ð °Ä¢éB±Ìrelative clause ͱÌ{Ì`ß
Å èAQuirk et al. ÍÀãAm/`/`cßðRÂÆà subordinationÆÊuïĢ
é±ÆÉÈéB
½¾µAQuirk et al.(1985, p.989ff)ÍAmßA`cßðÂé conjunction
ÌÝð subordinator ÆÄñÅ¢éBÖWã¼Ì that ÍAmßðÂé that ÆæÊ
µÄ subordinator ÅÍÈ subordination marker(p.1006) ÆÄÔB
The relative pronoun is to be distinguished from the subordinator
@@@ that, which does not operate as an element in the subordinate clause.
±Ì{ÅÍABurton-Roberts (pp.192ff)ÈÇƯlAmßA`cßA`ßð
(CVT{rÆ¢¤)ÐÆÂÌ`Å¡ÀÑÉÆç¦éBàÁÆàAmßð¶Ýo· that Íó
 (
( )ðìç¸A`ßð¶Ýo· that ÍK¸ó(
)ðìç¸A`ßð¶Ýo· that ÍK¸ó( )ðìéÆ¢¤_ÍdvÈá¢Å éB
)ðìéÆ¢¤_ÍdvÈá¢Å éB
 ¿ÈÝÉA±±Å¾¤ CVT Í¢íäé COMP ÆÍÙÈèAuÓ¡IɳFvÅ
ÍÈ¢BiªÏíéÆ¢¤±ÆÍÓ¡ªÏíéAÆ¢¤±Æ¾©çÅ éB
ø¢27-1-NT-(C)@mQ¶¬ÉæéÖWã¼Ì±ün
Ï`¶@ÌúAܾÏ`Æ¢¤TOª©RÉl¦çêÄ¢½ ÉÍA
LaPalombara, L.E.(pp.295-296)Ì "Multi-Base Embedding Transformation:
adjectivalization" Ìæ¤ÉÏ`ðQÂ̶ÉεÄÀsIÉs¤êíÌQ¶¬@
ªl¦çê½B
LaPalombara, L.E.(pp.281-314)ÍAMulti-Base Embedding Transformations
ƵÄÌRíÞð °Ä¢éB
(i) Adverbialization
1)a. He studies because of something.
b. He must pass the test.
c. ¨He studies because he must pass the exam.
(becauseÍsubordinator)
(ii) Adjectivalization
2)a. This is the house.
b. Jack built the house.
c. ¨That is the house that Jack built.
(iii) Nominalization
3)a. I realize something.
b. He will call me soon.
c. ¨I realize (the fact) that he will call me soon.
ܽA±êÆÍÊÉA Roberts et al.(p.181)Ìæ¤ÉA
4)a. The knight forgot his sword.
b. ¨ the knight who forgot his sword
Æ¢Á½A¶irj©çêCÉuæs{`eßvð¶Ýo·Ï` Rel iÖWßÏ
`jÆ¢¤l¦ûàoêµ½B
¿ÈÝÉA±±Å¾¤ CVT Í¢íäé COMP ÆÍÙÈèAuÓ¡IɳFvÅ
ÍÈ¢BiªÏíéÆ¢¤±ÆÍÓ¡ªÏíéAÆ¢¤±Æ¾©çÅ éB
ø¢27-1-NT-(C)@mQ¶¬ÉæéÖWã¼Ì±ün
Ï`¶@ÌúAܾÏ`Æ¢¤TOª©RÉl¦çêÄ¢½ ÉÍA
LaPalombara, L.E.(pp.295-296)Ì "Multi-Base Embedding Transformation:
adjectivalization" Ìæ¤ÉÏ`ðQÂ̶ÉεÄÀsIÉs¤êíÌQ¶¬@
ªl¦çê½B
LaPalombara, L.E.(pp.281-314)ÍAMulti-Base Embedding Transformations
ƵÄÌRíÞð °Ä¢éB
(i) Adverbialization
1)a. He studies because of something.
b. He must pass the test.
c. ¨He studies because he must pass the exam.
(becauseÍsubordinator)
(ii) Adjectivalization
2)a. This is the house.
b. Jack built the house.
c. ¨That is the house that Jack built.
(iii) Nominalization
3)a. I realize something.
b. He will call me soon.
c. ¨I realize (the fact) that he will call me soon.
ܽA±êÆÍÊÉA Roberts et al.(p.181)Ìæ¤ÉA
4)a. The knight forgot his sword.
b. ¨ the knight who forgot his sword
Æ¢Á½A¶irj©çêCÉuæs{`eßvð¶Ýo·Ï` Rel iÖWßÏ
`jÆ¢¤l¦ûàoêµ½B
 @@@@@ðjIÈoܩ羦ÎAi
@@@@@ðjIÈoܩ羦ÎAi ÍEQUIÅÍÈÚ®ÉæéÆ¢¤jQ¶¬
ÍEQUIÅÍÈÚ®ÉæéÆ¢¤jQ¶¬
 @ͳµ¢Bµ©µA³ºÅÍÌæ¤Èâè_ªµÎµÎ¨±éBÌ 1-a) Æ 1-b)
©çQ¶¬ðs¤ÆAQÂ̶AÂÜèA2-a)@Æ 2-b)@ª¶ÜêéB
1)a. I know a man.
b. The man speaks English very well.
2)a. I know a man who speaks English very well.
b. The man whom I know speaks English very well.
ê^¶ 1-a)É 1-b)ªß ÜêéÆ 2-a)ÉÈèA1-b) É 1-a) ªß ÜêéÆ
2-b) ª¾çêéÌÅ éBicf. ÀäA1982, p.123)
@@@@@µ©µAàÆàÆbÌiîñªThe man...ÈÌ©AI know...ÈÌ©j
ð³µ½±Ìw±@ÉÍâèª éBÞµëA2-a) Æ 2-b) ÍAÌ 3-a) Æ 3-b) ©
ç¶ÜêéÆl¦é׫Šë¤B
3)a. I know a man. He speaks English very well. ¨2-a)
b. The man speaks English very well. I know him. ¨2-b)
±±ÅÌ|CgÍAQÔÚ̶ªd¡êiman-he/him)ð trigger ɵÄ`ei`j
ßÉÏgµÄ¢éÆ¢¤_Å éB
ø¢27-2-NT-(A)@mArabic:
@ͳµ¢Bµ©µA³ºÅÍÌæ¤Èâè_ªµÎµÎ¨±éBÌ 1-a) Æ 1-b)
©çQ¶¬ðs¤ÆAQÂ̶AÂÜèA2-a)@Æ 2-b)@ª¶ÜêéB
1)a. I know a man.
b. The man speaks English very well.
2)a. I know a man who speaks English very well.
b. The man whom I know speaks English very well.
ê^¶ 1-a)É 1-b)ªß ÜêéÆ 2-a)ÉÈèA1-b) É 1-a) ªß ÜêéÆ
2-b) ª¾çêéÌÅ éBicf. ÀäA1982, p.123)
@@@@@µ©µAàÆàÆbÌiîñªThe man...ÈÌ©AI know...ÈÌ©j
ð³µ½±Ìw±@ÉÍâèª éBÞµëA2-a) Æ 2-b) ÍAÌ 3-a) Æ 3-b) ©
ç¶ÜêéÆl¦é׫Šë¤B
3)a. I know a man. He speaks English very well. ¨2-a)
b. The man speaks English very well. I know him. ¨2-b)
±±ÅÌ|CgÍAQÔÚ̶ªd¡êiman-he/him)ð trigger ɵÄ`ei`j
ßÉÏgµÄ¢éÆ¢¤_Å éB
ø¢27-2-NT-(A)@mArabic: ð¶¶È¢`e»n
ð¶¶È¢`e»n
 @@@@@Celce-Murcia & Larsen-Freeman(1983, p.361)ÉæêÎAArabic â Hebrew
@@@@@Celce-Murcia & Larsen-Freeman(1983, p.361)ÉæêÎAArabic â Hebrew
 ÅÍAÌæ¤È`e»ÉæÁÄ
ÅÍAÌæ¤È`e»ÉæÁÄ ð¶¶È¢`ªFßçêÄ¢éÌÅAÞçÌpê
ð¶¶È¢`ªFßçêÄ¢éÌÅAÞçÌpê
 ÉͱÌ`ÌÔᢪ½¢B
@@1) *Shirley called out to the boy that she knew him.
¿ÈÝÉAuâpêÅàÖWßÌÉæsƯ¶àÌðw·êªã¼Ì
`Åc¯µÄ¢é\¢ªµÎµÎ©çêévÆ¢¤BiöEnApp.65-66)
ÉͱÌ`ÌÔᢪ½¢B
@@1) *Shirley called out to the boy that she knew him.
¿ÈÝÉAuâpêÅàÖWßÌÉæsƯ¶àÌðw·êªã¼Ì
`Åc¯µÄ¢é\¢ªµÎµÎ©çêévÆ¢¤BiöEnApp.65-66)
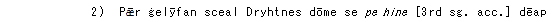 (=there he whom death carries off must trust in the Lord's
judgment) (Beowulf 441)
3) with other dyueres (=different people) that I know ther (=their)
names (PL II 426/31)
@@ 4) I ... whome nature and kynde(=nature) most specially ...
bynden(=bind) me to owe(=you) (PL II 317/12-3)
ø¢27-2-NT-(B)@mr|`]·q that Ì«n
@@@@@±Ì{ÅÍAr|`]·q that Ì«ÍAÌQÂÅ éB
@@@@@(i) ¯êmoF¯
(=there he whom death carries off must trust in the Lord's
judgment) (Beowulf 441)
3) with other dyueres (=different people) that I know ther (=their)
names (PL II 426/31)
@@ 4) I ... whome nature and kynde(=nature) most specially ...
bynden(=bind) me to owe(=you) (PL II 317/12-3)
ø¢27-2-NT-(B)@mr|`]·q that Ì«n
@@@@@±Ì{ÅÍAr|`]·q that Ì«ÍAÌQÂÅ éB
@@@@@(i) ¯êmoF¯
 (ii) Qnd moð
(ii) Qnd moð É
É
 ói
ói jªd¡íÉæèÅ«éÆ·é©Aãü|Ú®ÉæèÅ«éÆ·é©Íc_
jªd¡íÉæèÅ«éÆ·é©Aãü|Ú®ÉæèÅ«éÆ·é©Íc_
 ̪©êéƱëBiðjIÉÍÚ®ÉæéBcf.27-1-NT-(A))
@@@@@àµA¶irjÌ`e»ªd¡íÅÍÈãü[Ú®ÉæèÅ«éÆ·
éÆA{¶(5) ÍÌæ¤ÉÏíéB
1) (fish) {[the fish was caught by John]
@ « (thatð¶ªtÁj
(fish) {[that the fish was caught by John]
« (æQNPÉthatãüj
̪©êéƱëBiðjIÉÍÚ®ÉæéBcf.27-1-NT-(A))
@@@@@àµA¶irjÌ`e»ªd¡íÅÍÈãü[Ú®ÉæèÅ«éÆ·
éÆA{¶(5) ÍÌæ¤ÉÏíéB
1) (fish) {[the fish was caught by John]
@ « (thatð¶ªtÁj
(fish) {[that the fish was caught by John]
« (æQNPÉthatãüj
 (fish) {m
(fish) {m  that was caught by Johnn
that was caught by Johnn
 « ithatð¶ªÖÚ®j
« ithatð¶ªÖÚ®j
 (fish) {mthat
(fish) {mthat  was caught by Johnn
was caught by Johnn
 ¢¸êÌÄÅàAãL`ß̪͵§ÉÍ
¢¸êÌÄÅàAãL`ß̪͵§ÉÍ
 2) that
2) that  was caught by John
was caught by John
 Ìæ¤ÉÈèA
Ìæ¤ÉÈèA ªÜÜêÄ¢é±ÆÉÈéB
ªÜÜêÄ¢é±ÆÉÈéB
 @@@ ãü|Ú®æèd¡íðx·é©àµêÈ¢áƵÄÍAÀäi1996,
p.248)ÌÌ᪠éªA
@@ 3) The house which Tom broke the window of is Mr.smith's.
êûAÌ McCawley, J.D. (1988)ÌáÍAPÈd¡íÅÍà¾Å«È¢B
@@@ ãü|Ú®æèd¡íðx·é©àµêÈ¢áƵÄÍAÀäi1996,
p.248)ÌÌ᪠éªA
@@ 3) The house which Tom broke the window of is Mr.smith's.
êûAÌ McCawley, J.D. (1988)ÌáÍAPÈd¡íÅÍà¾Å«È¢B
 @@@@@@@1)a. the person who [John says that [you talked to
@@@@@@@1)a. the person who [John says that [you talked to  ]] (p.435)
]] (p.435)
 b. *the policeman who [FBI is looking for the person who killed
b. *the policeman who [FBI is looking for the person who killed

 ]
]
 2) *the guy who they don't know whether
2) *the guy who they don't know whether  wants to come (p.444)
ø¢27-2-NT-(C)@mSíÞÌ`±IÈ
wants to come (p.444)
ø¢27-2-NT-(C)@mSíÞÌ`±IÈ n
n
 @@@@@©µÄA±Ì{ÅÍAÌSÂÌ«Å`±Iiobligatory)È
@@@@@©µÄA±Ì{ÅÍAÌSÂÌ«Å`±Iiobligatory)È  ªoê
ªoê
 ·é±ÆÆÈéB
·é±ÆÆÈéB
 (i) uÌg[(ex. be-en {VZ{
(i) uÌg[(ex. be-en {VZ{ )
)
 (ii) rÌg[(ex. What do you want
(ii) rÌg[(ex. What do you want  ?)
?)
 (iii) uÌ]·(ex. something to eat
(iii) uÌ]·(ex. something to eat  )
)
 (iv) rÌ]·(ex. a book that I bought
(iv) rÌ]·(ex. a book that I bought  )
ø¢27-2-NT-(D)@m
)
ø¢27-2-NT-(D)@m w±ÌÓ`Æâè_n
w±ÌÓ`Æâè_n
 @@@@@¶irjÌ`e»ðw±·éÛÉ
@@@@@¶irjÌ`e»ðw±·éÛÉ  ðmF·éÆ¢¤±ÆÍAÌæ¤È
ðmF·éÆ¢¤±ÆÍAÌæ¤È
 ñ¶ðo³È¢Æ¢¤øʪ èA
@@@@@@@1) *Shirley called out to be the boy that she knew him.
(Celce-Murcia & Larsen-Freeman, 1983, p.361)
ñ¶ðo³È¢Æ¢¤øʪ èA
@@@@@@@1) *Shirley called out to be the boy that she knew him.
(Celce-Murcia & Larsen-Freeman, 1983, p.361)
 êûÅA
êûÅA ðl¦é±ÆÉæèAÌ 2-a) Æ 2-b) ÌæʪūéÆ¢¤bgª
ðl¦é±ÆÉæèAÌ 2-a) Æ 2-b) ÌæʪūéÆ¢¤bgª
 éB
2)a. Winter is gone.
éB
2)a. Winter is gone.
 b. The cockroach was killed
b. The cockroach was killed  .
.
 @@@@@³çÉAÌ 3-a) Ì ¢Ü¢³ÍA3-b) Æ 3-c) ðl¦é±ÆÅà¾Å«
éB
3)a. I found the purse that I had stolen.
@@@@@³çÉAÌ 3-a) Ì ¢Ü¢³ÍA3-b) Æ 3-c) ðl¦é±ÆÅà¾Å«
éB
3)a. I found the purse that I had stolen.
 b. I found the purse that I had
b. I found the purse that I had  stolen. iªÜê½àzj
stolen. iªÜê½àzj
 c. I found the purse that I had stolen
c. I found the purse that I had stolen  . iªñ¾àzj
. iªñ¾àzj
 @@@@@µ©µAêûÅAÌæ¤È¢Â©Ìâè_à éBܸA
@@@@@µ©µAêûÅAÌæ¤È¢Â©Ìâè_à éBܸA ð¶Ýo³
ð¶Ýo³
 È¢r|`]·qª éB
@@@@@@@4) She looked as if she had seen a ghost or something.
5) I'll never forget his surprise when we told him. ¼g, p.73
È¢r|`]·qª éB
@@@@@@@4) She looked as if she had seen a ghost or something.
5) I'll never forget his surprise when we told him. ¼g, p.73
 ܽAÌæ¤É
ܽAÌæ¤É ðÂàÌƽȢàÌ̼ûªe³êé`e»ª éB
ðÂàÌƽȢàÌ̼ûªe³êé`e»ª éB
 6)a. the now-I-can-tell-
6)a. the now-I-can-tell- story
story
 b. the now-I-can-tell-you story
c. the now-I-can-tell-it story
ø¢27-3-NT-(A)@mr|`]·q(ÖWã¼jÌIðFthat/which/who(m)n
Àäi1994, p.739-750)( vñjÉæêÎAthat Æ which/who(m) ÆÌ
ðÖÉÍÌæ¤È|ª éB
(i) ñ§ÀIp@ÅÍAthatsÂBwhich/who(m)ªgíêéB
(ii) æsªlÌÆ« who(m)AlÈOÌÆ«whichBthat ͼûnjB
(iii) åiÌ who Í that æèDÜêéBiæsªÎºñƵ½¨Ì
Æ«thatàÂj
(iv) ÚIêÅÍ who(m)/which æè that ªDÜêéB
(v) all, best, last, everything ÈÇÌãÅÍ that ªDÜêéB
@@@@±Ì{ÅÍAr|`]·qƵÄܸ that ð±üµA»Ìu¾¢·¦\»v
ÆµÄ which/who/whom ð±ü·éBµ½ªÁÄA³ºÅ̱üÍAÌæ¤É
Èë¤B
@@@@@@(i) §Àp@Ì that.
(ii) æsªlÈçwho(m)Öioptional)
(iii) æsªlÈOÈçwhichÖioptional)
(iv) *ñ§ÀIp@Ì thatilÈçjwho(m)Öiobligatory)
(v) *ñ§ÀIp@Ì thatilÈOÈçjwhich Öiobligatory)
@¿ÈÝÉAÌ 1) Ì when Ìæ¤ÈA¢íäéAÖW̱üÍA
2) Ìæ¤ÈàÌÆÈë¤B
1) The day will come when we have to work only four days a week.
2) that...in ¨ which...in ¨ in which ... ¨ when ...
@@@@@ȨAÈw¶@Åͱ±Å¾¤r|`]·qÌ that Æ whichÈÇÆð
ʨƵĵ¤§êà éBicf.de Chene p.147, öEn p.5)
ø¢27-3-NT-(B)@m¯ê«F¯il©¨©ÈÇjÌ ¢Ü¢³n
@@@@@that ð which/who(m) ɾ¢·¦éêAd¡í³ê½¼imjªlÅ
驨Šé©ÍdvÈîñÆÈéB½¾µAl©¨©ÌæʪÂËɵ§Éßçê
éÆ¢¤í¯ÅÍÈ¢BÌ 1) ÅÍA¸_IY¨ÆµÄÌ{ƨIY¨ÆµÄÌ{ð
f«ãÌ¸êª éÉàS縯ê«Ìð(identity condition)ÌàÆÅFßĨèA
(ÀäA1987, p.418)
1) This book, which John wrote, weighs five pounds.
Ì athlete ÍlÆ¢¤æèóÔƵÄÆç¦çêÄ¢éB
2) He is not the athlete that[*who] he was when he was at college.
@@@@@@@@@@@ (ÀäA1994, p.740)
Ì 3) ÅÍAÊí she/her Ť¯çêé ship ªAwho(m) ÅÍÈ which ð±¢Ä
¢éB
3)@The captain told us about the ship which[*who(m)] he commanded.
@@@@@@@@@@@ (ÀäA1994, p.739)
@@@@@Íd¡í³ê½ªªK¸µà¼imjÆ;¦È¢áÅ éB
4) I'm delighted, which I know you're not. (Kaplan, J.P. p.301)
@@@@@ÌáÅAwhich ª³·àÌÍO¶S̪¼»³ê½àÌÅ éB
5) She signed the letter herself, which was a serious infringement
of the rules. (ÀäA1994, p.734)
ø¢27-3-NT-(C)@mr|`]·qÌwhichÈÇÆu|`]·qÌ to n
@@@@@ÌáÅÍAr|`]·qÌ which/who Æu|`]·qÌ to ª
üµ¢pYð©¹Ä¢éB
b. the now-I-can-tell-you story
c. the now-I-can-tell-it story
ø¢27-3-NT-(A)@mr|`]·q(ÖWã¼jÌIðFthat/which/who(m)n
Àäi1994, p.739-750)( vñjÉæêÎAthat Æ which/who(m) ÆÌ
ðÖÉÍÌæ¤È|ª éB
(i) ñ§ÀIp@ÅÍAthatsÂBwhich/who(m)ªgíêéB
(ii) æsªlÌÆ« who(m)AlÈOÌÆ«whichBthat ͼûnjB
(iii) åiÌ who Í that æèDÜêéBiæsªÎºñƵ½¨Ì
Æ«thatàÂj
(iv) ÚIêÅÍ who(m)/which æè that ªDÜêéB
(v) all, best, last, everything ÈÇÌãÅÍ that ªDÜêéB
@@@@±Ì{ÅÍAr|`]·qƵÄܸ that ð±üµA»Ìu¾¢·¦\»v
ÆµÄ which/who/whom ð±ü·éBµ½ªÁÄA³ºÅ̱üÍAÌæ¤É
Èë¤B
@@@@@@(i) §Àp@Ì that.
(ii) æsªlÈçwho(m)Öioptional)
(iii) æsªlÈOÈçwhichÖioptional)
(iv) *ñ§ÀIp@Ì thatilÈçjwho(m)Öiobligatory)
(v) *ñ§ÀIp@Ì thatilÈOÈçjwhich Öiobligatory)
@¿ÈÝÉAÌ 1) Ì when Ìæ¤ÈA¢íäéAÖW̱üÍA
2) Ìæ¤ÈàÌÆÈë¤B
1) The day will come when we have to work only four days a week.
2) that...in ¨ which...in ¨ in which ... ¨ when ...
@@@@@ȨAÈw¶@Åͱ±Å¾¤r|`]·qÌ that Æ whichÈÇÆð
ʨƵĵ¤§êà éBicf.de Chene p.147, öEn p.5)
ø¢27-3-NT-(B)@m¯ê«F¯il©¨©ÈÇjÌ ¢Ü¢³n
@@@@@that ð which/who(m) ɾ¢·¦éêAd¡í³ê½¼imjªlÅ
驨Šé©ÍdvÈîñÆÈéB½¾µAl©¨©ÌæʪÂËɵ§Éßçê
éÆ¢¤í¯ÅÍÈ¢BÌ 1) ÅÍA¸_IY¨ÆµÄÌ{ƨIY¨ÆµÄÌ{ð
f«ãÌ¸êª éÉàS縯ê«Ìð(identity condition)ÌàÆÅFßĨèA
(ÀäA1987, p.418)
1) This book, which John wrote, weighs five pounds.
Ì athlete ÍlÆ¢¤æèóÔƵÄÆç¦çêÄ¢éB
2) He is not the athlete that[*who] he was when he was at college.
@@@@@@@@@@@ (ÀäA1994, p.740)
Ì 3) ÅÍAÊí she/her Ť¯çêé ship ªAwho(m) ÅÍÈ which ð±¢Ä
¢éB
3)@The captain told us about the ship which[*who(m)] he commanded.
@@@@@@@@@@@ (ÀäA1994, p.739)
@@@@@Íd¡í³ê½ªªK¸µà¼imjÆ;¦È¢áÅ éB
4) I'm delighted, which I know you're not. (Kaplan, J.P. p.301)
@@@@@ÌáÅAwhich ª³·àÌÍO¶S̪¼»³ê½àÌÅ éB
5) She signed the letter herself, which was a serious infringement
of the rules. (ÀäA1994, p.734)
ø¢27-3-NT-(C)@mr|`]·qÌwhichÈÇÆu|`]·qÌ to n
@@@@@ÌáÅÍAr|`]·qÌ which/who Æu|`]·qÌ to ª
üµ¢pYð©¹Ä¢éB
 @@@@@@ 1)a. a shovel to dig the hole with
@@@@@@ 1)a. a shovel to dig the hole with  (McCawley, J.D., p.429)
(McCawley, J.D., p.429)
 b. a shovel which you can dig the hole with
b. a shovel which you can dig the hole with 
 2)a. the person to give the money to
2)a. the person to give the money to 
 b. the person who you should give the money to
b. the person who you should give the money to 
 @@@@@½¾µAwhich/who ÈÇÆ to ª¤¶·éA¢íäéA infinitival
relatives(McCawley, J.D.1988, pp.429ff)ÅÍA»Ì¤NÉ墀 heavy restrictions
ª¶Ý·éB
@@@@@@@3)a. a shovel with which to dig the hole (p.429)
b. a hole (*which) to fill with earth
4)a. a shovel for us to dig the hole with
b. *a shovel with which for us to dig the hole
5)a. a priest (for us) to be blessed by (p.430)
b. a priest by whom to be blessed
6)a. a book in which (*for Al) to find the answers to his questions
b. a book for Al to find the answers to his questions in (p.452)
±êçÍAwhich/who ÈÇÆ to ðÆàÉ`ð¶Ýo·]·qÆÊuïé±Ì{ÅͪÍ
ÍÞ©µ¢Bicf.McCawley, J.D. 1988, p.435/p.444 é¢ÍÀäA1982, p.125_
uÌÖWã¼j
ø¢27-4-NT@m§ÀIp@(restrictive)Æñ§ÀIp@(non-restrictive)n
@@@@@Àäi1994, p.735)ÉæêÎA§ÀIÖWß(restrictive)ÍAæsÉ
æÁÄwµ¦³êéàÌðA¯¶NX̼̬õ©çæʵAÁè»·é½ßÉKv
Èîñð^¦éB
@@@@@@@1) The essay I read yesterday was interesting.
êûAñ§ÀIÖWß(nonrestrictive)ÍA·ÅÉí©ÁÄ¢éw¦¨É¢Äâ«
IÈîñð^¦éÌÅA±ÌßðȪµÄàw¦¨ÌÁè»Ée¿ÍÈ¢B
@@@@@@@2) My sister, whose name is Maud, lives in Newenden.
@@@@ܽAÓ¡IÈð©ç·éÆA§ÀIÖWßÍæsƯ¶îñÌPÊÉ
®µÄ¢éÌÉεÄAñ§ÀIÖWßÍæsÆÊÌîñPÊÉ®µÄ¢éBöE
n(p.67)Ì\»ðØèêÎA§ÀßÍæsÉÖ·éùmÌîñðAñ§ÀßÍæs
ÉÖ·éVµ¢îñðñ¦·éAÆÈéB
@@@@@µ½ªÁÄAÌ 3-a) ÅÍAone Í violin that once belonged to
Heifetz@ð³·ÌÉεA3-b) ÅÍAviolin ¾¯ð³·Æ¢¤±ÆÉÈéB
@@@@@@@3)a. Tom has a violin that once belonged to Heifetz, and Jane
has one too. @@@(McCawley, J.D. 1988, p.420)
b. Tom has a violin, which once belonged to Heifetz, and Jane
has one too.
@@@@@½¾µAwKp¶@ÅÅàdvÈÌÍAñ§ÀIÖWßÌêÍA¼O é
¢ÍOãÉA
@@@@@@@(i) x~ªu©êéibµ±ÆÎj
@@@@@@ (ii) R}i,)ªu©êéi«±ÆÎj
Æ¢¤±ÆÅ éB
@@@@@à¿ëñAãwKÒÌêÉÍA̱ÆðméKvª ë¤B
@@@@@@@(i) ñ§ÀIÖWßÅÍ that ÍgíÈ¢
@@@@@@ (ii) §ÀIÖWßÍÅL¼impro)ÉÍ©©çÈ¢
ø¢27-5-NT@mr|`]·qÌȪi[ÖWjn
@@@@@öEn(p.65)ivñjÉæêÎA[ÖWÍAÙÆñÇåiÉÀç
êÄ¢½B»êªAÈãæɦAPW¢IÉüÁÄêÊÉpê½BãíÁÄÚIêÌ
[ÖWªo»APU|V¢IÉ}µ½BíɧÀßÅ éB
@@@@@»ãpêÅÍAÚIiÌÖWã¼ÍµÎµÎȪ³êéªAåiÌÖWã¼
ÌȪÍA¶É there is ªÜÜêÄ¢éêɽ AÙÆñÇ ûêÌÉÀçêéB
(ÀäA1996, p.254) [ÈÍÖWã¼ÌȪ³êÄ¢éÊuð¦·]
1) This is the highest building È there is in Paris.
2) There is somebodyÈ wants to see you.
@@@@@ܽAÀäi1987, p.396)ÉæêÎAÖWã¼ÌÈ¢ithat-lessjÖWß
ÍAÖW㼪¾¦³êÄ¢éßÆÓ¡ªÙÈÁÄ¢éÆ¢¤wEª éB
@@@@3)a. John gave a book {that/which} he wrote to Mary.
@@@@@½¾µAwhich/who ÈÇÆ to ª¤¶·éA¢íäéA infinitival
relatives(McCawley, J.D.1988, pp.429ff)ÅÍA»Ì¤NÉ墀 heavy restrictions
ª¶Ý·éB
@@@@@@@3)a. a shovel with which to dig the hole (p.429)
b. a hole (*which) to fill with earth
4)a. a shovel for us to dig the hole with
b. *a shovel with which for us to dig the hole
5)a. a priest (for us) to be blessed by (p.430)
b. a priest by whom to be blessed
6)a. a book in which (*for Al) to find the answers to his questions
b. a book for Al to find the answers to his questions in (p.452)
±êçÍAwhich/who ÈÇÆ to ðÆàÉ`ð¶Ýo·]·qÆÊuïé±Ì{ÅͪÍ
ÍÞ©µ¢Bicf.McCawley, J.D. 1988, p.435/p.444 é¢ÍÀäA1982, p.125_
uÌÖWã¼j
ø¢27-4-NT@m§ÀIp@(restrictive)Æñ§ÀIp@(non-restrictive)n
@@@@@Àäi1994, p.735)ÉæêÎA§ÀIÖWß(restrictive)ÍAæsÉ
æÁÄwµ¦³êéàÌðA¯¶NX̼̬õ©çæʵAÁè»·é½ßÉKv
Èîñð^¦éB
@@@@@@@1) The essay I read yesterday was interesting.
êûAñ§ÀIÖWß(nonrestrictive)ÍA·ÅÉí©ÁÄ¢éw¦¨É¢Äâ«
IÈîñð^¦éÌÅA±ÌßðȪµÄàw¦¨ÌÁè»Ée¿ÍÈ¢B
@@@@@@@2) My sister, whose name is Maud, lives in Newenden.
@@@@ܽAÓ¡IÈð©ç·éÆA§ÀIÖWßÍæsƯ¶îñÌPÊÉ
®µÄ¢éÌÉεÄAñ§ÀIÖWßÍæsÆÊÌîñPÊÉ®µÄ¢éBöE
n(p.67)Ì\»ðØèêÎA§ÀßÍæsÉÖ·éùmÌîñðAñ§ÀßÍæs
ÉÖ·éVµ¢îñðñ¦·éAÆÈéB
@@@@@µ½ªÁÄAÌ 3-a) ÅÍAone Í violin that once belonged to
Heifetz@ð³·ÌÉεA3-b) ÅÍAviolin ¾¯ð³·Æ¢¤±ÆÉÈéB
@@@@@@@3)a. Tom has a violin that once belonged to Heifetz, and Jane
has one too. @@@(McCawley, J.D. 1988, p.420)
b. Tom has a violin, which once belonged to Heifetz, and Jane
has one too.
@@@@@½¾µAwKp¶@ÅÅàdvÈÌÍAñ§ÀIÖWßÌêÍA¼O é
¢ÍOãÉA
@@@@@@@(i) x~ªu©êéibµ±ÆÎj
@@@@@@ (ii) R}i,)ªu©êéi«±ÆÎj
Æ¢¤±ÆÅ éB
@@@@@à¿ëñAãwKÒÌêÉÍA̱ÆðméKvª ë¤B
@@@@@@@(i) ñ§ÀIÖWßÅÍ that ÍgíÈ¢
@@@@@@ (ii) §ÀIÖWßÍÅL¼impro)ÉÍ©©çÈ¢
ø¢27-5-NT@mr|`]·qÌȪi[ÖWjn
@@@@@öEn(p.65)ivñjÉæêÎA[ÖWÍAÙÆñÇåiÉÀç
êÄ¢½B»êªAÈãæɦAPW¢IÉüÁÄêÊÉpê½BãíÁÄÚIêÌ
[ÖWªo»APU|V¢IÉ}µ½BíɧÀßÅ éB
@@@@@»ãpêÅÍAÚIiÌÖWã¼ÍµÎµÎȪ³êéªAåiÌÖWã¼
ÌȪÍA¶É there is ªÜÜêÄ¢éêɽ AÙÆñÇ ûêÌÉÀçêéB
(ÀäA1996, p.254) [ÈÍÖWã¼ÌȪ³êÄ¢éÊuð¦·]
1) This is the highest building È there is in Paris.
2) There is somebodyÈ wants to see you.
@@@@@ܽAÀäi1987, p.396)ÉæêÎAÖWã¼ÌÈ¢ithat-lessjÖWß
ÍAÖW㼪¾¦³êÄ¢éßÆÓ¡ªÙÈÁÄ¢éÆ¢¤wEª éB
@@@@3)a. John gave a book {that/which} he wrote to Mary.
 b. John gave a book
b. John gave a book  he wrote to Mary.
he wrote to Mary.
 3-a) ̶ÍA3-b) Éç×ÄuÙ©Éà{ª éÌÉ©ªÌ¢½{ðvÆ¢¤Üݪ
¢Æ¢¤B
@@@@@ ¼ÒÌÔÉÓ¡Ìᢪ éÆ·êÎAQíÞÌÖWßÍAêûª¼û©çA
ÖWã¼ÌȪÉæÁÄh¶³êéÌÅÍÈAß©çÊÂÌàÌÅ é
Æ·é©ûªÂ\ÉÈéB
@@@@@±üEw±Æ¢¤Ï_©ç¾¦ÎA[ÖWðÂA¢íäéAuÚGßv
©çüéû@ÆAthat/which ÈÇÌÖWðÂ`e©çüèA»ÌȪƢ¤`Å
ÚGßÌà¾Éüéû@ƪ éBpêÌúíïbÅÍA³|IÉÚGߪ½gíêé
ÌÅpxðd·é§êÅÍOÒðA\¢ðÉd_ðu§êÅÍãÒðÆé±ÆÆÈ
ë¤B
ø¢27-6-NT@mÖWã¼im{CVT)ÌwhatÆ^âiEPDjÌwhatn
@@@@@McCawley, J.D. (1988, p.431) ÍAÌ 1-a) Ì whatßð interrogative
complementA1-b) Ì whatßð free relative ÆÄÑA
@@@@@@ 1)a. I'll ask what he's selling. (Interrogative complement)
b. I'll buy what he's selling.(Free relative)
Bresnan and Grimshaw(1978) ÉæêÎAfree relative ¾¯ª whatever Å̾¢©¦ð
·Æ¢¤B
@@@@@@@ 2)a. I'll buy whatever he's selling.
b. *I'll ask whatever he's selling.
@@@@@êÊÉAknow, guess ÈÇÌãÉÍ indirect question ªAwear,
borrow ÈÇÌãÉÍ free relative ª±Æ¾¦éBiBaker, C.L. 1989, p.226)
½¾µA`ßð¶Ýo· that/which ÈÇÆAmßð¶Ýo·±Ì what Æð¯¶uÖW
ã¼vÆÄÔ±ÆÍwKp¶@ÅÍâß½¢àÌÅ éB
@@@@@¿ÈÝÉAHamburger and Crain(1982) iin Givon, T. p.10) ÉæêÎARË
È~Ì grammatical inventiveness ÌáƵÄA
@@@@@@@3) This is my did it. (This is what I did.)
4) Look-a my made. (Look at what I made.)
3-a) ̶ÍA3-b) Éç×ÄuÙ©Éà{ª éÌÉ©ªÌ¢½{ðvÆ¢¤Üݪ
¢Æ¢¤B
@@@@@ ¼ÒÌÔÉÓ¡Ìᢪ éÆ·êÎAQíÞÌÖWßÍAêûª¼û©çA
ÖWã¼ÌȪÉæÁÄh¶³êéÌÅÍÈAß©çÊÂÌàÌÅ é
Æ·é©ûªÂ\ÉÈéB
@@@@@±üEw±Æ¢¤Ï_©ç¾¦ÎA[ÖWðÂA¢íäéAuÚGßv
©çüéû@ÆAthat/which ÈÇÌÖWðÂ`e©çüèA»ÌȪƢ¤`Å
ÚGßÌà¾Éüéû@ƪ éBpêÌúíïbÅÍA³|IÉÚGߪ½gíêé
ÌÅpxðd·é§êÅÍOÒðA\¢ðÉd_ðu§êÅÍãÒðÆé±ÆÆÈ
ë¤B
ø¢27-6-NT@mÖWã¼im{CVT)ÌwhatÆ^âiEPDjÌwhatn
@@@@@McCawley, J.D. (1988, p.431) ÍAÌ 1-a) Ì whatßð interrogative
complementA1-b) Ì whatßð free relative ÆÄÑA
@@@@@@ 1)a. I'll ask what he's selling. (Interrogative complement)
b. I'll buy what he's selling.(Free relative)
Bresnan and Grimshaw(1978) ÉæêÎAfree relative ¾¯ª whatever Å̾¢©¦ð
·Æ¢¤B
@@@@@@@ 2)a. I'll buy whatever he's selling.
b. *I'll ask whatever he's selling.
@@@@@êÊÉAknow, guess ÈÇÌãÉÍ indirect question ªAwear,
borrow ÈÇÌãÉÍ free relative ª±Æ¾¦éBiBaker, C.L. 1989, p.226)
½¾µA`ßð¶Ýo· that/which ÈÇÆAmßð¶Ýo·±Ì what Æð¯¶uÖW
ã¼vÆÄÔ±ÆÍwKp¶@ÅÍâß½¢àÌÅ éB
@@@@@¿ÈÝÉAHamburger and Crain(1982) iin Givon, T. p.10) ÉæêÎARË
È~Ì grammatical inventiveness ÌáƵÄA
@@@@@@@3) This is my did it. (This is what I did.)
4) Look-a my made. (Look at what I made.)
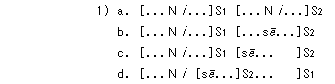 iS ͶAmi ͯêl^¨ðw¦·é¼ð¦·j
o_ÆÈéÌÍA¯¶àÌðw·¼ðÜñ¾QÂ̶ÌÊÚ±\¢1-a)
Å éBQÂÚÌ¶É é¯êw¦Ì¼ÍAJèÔµðð¯é½ßÉ1-b) Ìæ¤Éã
¼»³êA³çÉr2̶ªÖ®©³ê1-c)ÆÈÁ½B±êªÖWß\¢Ì´^Å éB
ÌiKÉÈéÆAr2S̪iå¶j̼iæsj̼ãÌÊuÉ®©³ê 1-d)
ÆÈéB±ÌöEnÌðàÌv_ÍÌQ_Å éB
@@(i) ÈOÍ]®\¢ªÈ©Á½Biand ÉæéÊ\¢ÌÝj
iS ͶAmi ͯêl^¨ðw¦·é¼ð¦·j
o_ÆÈéÌÍA¯¶àÌðw·¼ðÜñ¾QÂ̶ÌÊÚ±\¢1-a)
Å éBQÂÚÌ¶É é¯êw¦Ì¼ÍAJèÔµðð¯é½ßÉ1-b) Ìæ¤Éã
¼»³êA³çÉr2̶ªÖ®©³ê1-c)ÆÈÁ½B±êªÖWß\¢Ì´^Å éB
ÌiKÉÈéÆAr2S̪iå¶j̼iæsj̼ãÌÊuÉ®©³ê 1-d)
ÆÈéB±ÌöEnÌðàÌv_ÍÌQ_Å éB
@@(i) ÈOÍ]®\¢ªÈ©Á½Biand ÉæéÊ\¢ÌÝj